平倉圭プレゼンテーション ジャーキングという認識論(エピステモロジー)
■ジャーキングという認識論(エピステモロジー)
平倉
私は映画の研究をしています。映画は映画館では、座って観ないといけない。プロジェクションされた映像に向かって、じっと静止していなければならない。それが私にはときどき苦痛です。私はできれば映画は動き回りながら観たい。今回映像祭で話すにあたって、映像の問題を映画館的な場所から切り離したい、プロジェクションと静止した身体という組み合わせから切り離して考えてみたいと思いました。そこで導入したいと思うのが蜘蛛のことです。
これはジョロウグモという、都会でもよく見られる蜘蛛です。体が大きく、特殊な3層構造で支えられた網をもちます。まずこの映像を見てください。
昨年の秋に私はずっとジョロウグモの観察と撮影をしていました。虫が網にかかると蜘蛛は近づいていく。虫だけではなく、葉っぱなどをかけても蜘蛛は近づいてきます。このとき、蜘蛛はたんに葉っぱを虫と間違えているわけではない。ジョロウグモは、顎で葉っぱのついた網を切り抜いていきます[fig.4]。
無理やり葉を外すと網自体が壊れてしまうので、葉の周りを顎で切りながら落とす。器用ですね。この後穴の周りを簡単に補修して、また真ん中に戻る。この蜘蛛の網は、少し比喩的な言い方をすると、蜘蛛にとっての「拡張された身体」になっています。このあたりから映像の問題を考えてみたいと思います。
さきほど、認識論(エピステモロジー)という言葉が何度も出てきました。ベイトソンに「エピステモロジーの正気と狂気」というエッセイ(『精神の生態学』所収)がありますが、その冒頭に次のようなやりとりがあります。
会場に集まった人々にベイトソンが「いまわたしが見えるということに異存のない方はどのくらいいますか?」と問いかける。たくさんの人が手を挙げる。するとベイトソンは、みなさん狂ってますねと言う。なぜなら人が見ているのは、ベイトソンの「イメージ」であって、ベイトソン「そのもの」ではないからです。人は感覚器官を通して得られた情報を合成してベイトソンの「イメージ」を作り出しているにすぎない。それがエピステモロジーということです。認識論とは、私が経験しているのは世界「そのもの」ではなく、認識を通して獲得された世界の「イメージ」にすぎないということです。
この認識論の問題を、鮮烈な、そしてある種「映画館」的な比喩によって考察したのが、プラトンです。プラトンは『国家』のなかで次のような比喩を示しています[fig.5]。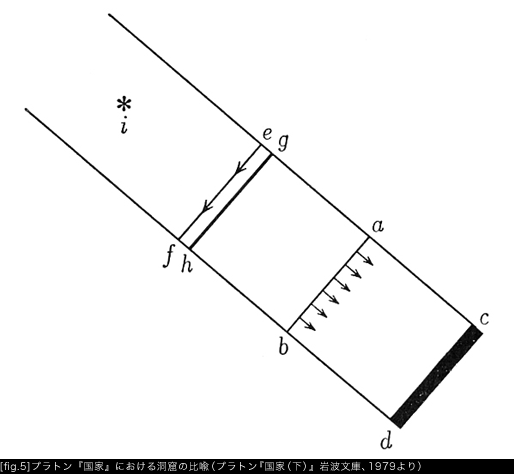
地下に向かう洞窟がある。普通の人間は、洞窟のa-bと書かれた線上に座っている。そこに座っている人たちは、手足を縛りつけられ、頭も固定されていて動くことができない。頭は洞窟の底のほうに向けられている。c-dの面です。iのポイントには光点が設定されており、e-fというところにちょっとした通路があります。通路には低い塀が設置されており、そこを謎の影絵遣いたちが、頭上に様々な物を掲げながら通る。すると、iに照らされた物の影が、c-dの面に映る。a-bに座っている人は、c-dに映る影絵を見ることになるわけです。プラトンはこのモデルを使って、私たちの世界認識を説明します。つまり私たちは、世界を見ているのではなく、世界の影絵を、プロジェクションを見ているというのです。そして哲学をするとは、a-bに縛り付けられた私たちが頭の向きを変え、拘束具を外し、この洞窟の外へとでていくことにほかならない。
洞窟の外に出ることはプラトンにとって大きな問題です。なぜなら、私の見ている世界がたんなる影絵にすぎなかったら、現実と錯覚とを、在るものと在る「ように見える」ものとを、区別できなくなってしまうからです。そうすればいかなる真実の認識も、善の実践も可能ではなくなってしまう。真実「のように見えるもの」、善「のように見える」ものにしか到達できなくなってしまう。そして私たちが感覚器官を通して世界を認識する限り、この、「ように見える」ことの洞窟の外に出る術は存在しない。洞窟とは私たちの感覚器官のことです。私たちは、感覚を信頼することをやめなければ、この洞窟の外に出ることはできない。でも本当にそうなのか。
もうひとりの哲学者を導入しましょう。ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインは日記のなかに次のような文を書き付けています。「もし対空砲が彩色されていて、上空からは木や石のように見え、本当の輪郭がわからなくなり、その代わりに偽の輪郭がこしらえてあったならば、この物を判別するのは如何に難しいことか。次のように言う者も想像できる。つまり、全ては偽の輪郭なのだ。だからこれが本当の輪郭だというものはないのだ。だがそこには確固とした本当の形があるのであり、ただ普通の方法ではそれは見つけられない。(…中略…)カブト虫が木の葉の様に見えるとはなんという自然のいたずらだろう。でも、その場合にも本当のカブト虫は存在するのであり、現実の木の葉が存在するわけではない」。
ここでウィトゲンシュタインは2つのことを述べています。ひとつは、人が認識論に閉じ込められているということ。すなわち、対空砲が完全にカモフラージュされていたら私には見えない。見えないという認識の内側に私は閉じ込められてしまう。すると私の認識にとって、対空砲は存在しないのだと言ってもいい。対空砲がそこにはない、という認識から逃れる術は、私の認識の内側からは供給されない。しかしここで重要なことは、問題になっているのが「対空砲」だということです。「対空砲」は、私を殺しうる。たとえ私がそこには何もないと思っていたとしても、対空砲から弾が飛んできたら、私は死んでしまう。つまり私の脳が構成している世界、そこに対空砲はないということのうちに私が閉ざされているはずの認識論的世界の内側から弾が飛んできて、私が破壊されてしまうのです。これは認識論的世界の閉鎖性が外部に向かって開かれる瞬間です。
もうひとつこの文で重要なのは、人間以外の動物にも映像の問題があるという示唆です。昆虫が木の葉の「ように見える」とは、まさに認識論の問題にほかならない。認識論に閉じ込められるということは、プラトンの洞窟の影絵に見る通りまさに映像の問題です。私たちは世界を見ているのではなくて、世界の映像を見ている。それがプラトンの示したことです。動物にもそれはありうる。カブトムシが木の葉に見えてしまう。あるいは、ハナカマキリが花に見えてしまい、そこにとまろうとした蝶が食べられてしまう。見間違うということは、動物が認識論的閉鎖性のうちに閉じ込められているということを意味しています。しかし食べられてしまう蝶は、食べられることによって、自らの認識論的世界の外に出ると言うこともできる。対空砲のときと同じです。蝶は、自分の認識がつくりだしていた世界の外に出ると同時に食べられ、食べられることで外に出る。そのようなところで、ウィトゲンシュタインは認識論の破れを語っているように見えます。
蜘蛛の話に戻ります。蜘蛛を観察していると、しかし、認識論的閉鎖性の外に連れ出されるのは、必ずしも生死にかかわる瞬間だけではないということがわかります。ジョロウグモは、とても大きく成長する蜘蛛ですが、よく見ていると小さなハエを主食にしている。その蠅を食べるときに、ちょっと奇妙な動きをします。よく見ていてください。
──ジョロウグモのジャーキング──[fig.6]
最後に食べた小さな点のようなものが蠅なのですが、蠅に近づいていくときに、ジョロウグモの脚が変な動きをしていたことに気づかれたでしょうか。これはジャーキング(痙攣)と呼ばれる行動です。蜘蛛はそんなに目がよくない。小さい蠅のような虫が網の上に止まったときに、止まったということはわかっても、その場所は正確にはわからない。そのとき、蜘蛛は自分の脚で網を揺らします。そうすることで、自分の起こした振動と返ってくる振動から、どこに蠅が止まっているのかを知覚することができる。そのために、網を何度もはじいて震わせるのです。
この行動は私にとってはとても興味深いものです。蜘蛛もまた動物なので、自分の認識論的世界に閉ざされている。けれども私たちは、プラトンが考えていたようなまったく動けない映画館のような場所で、世界を知覚しているわけではありません。少なくとも蜘蛛はちがう。蜘蛛はずっと椅子に座っているわけではなく、自分の身体で、自分の周囲にある環境を揺らすことができる。その揺らされている環境は、蜘蛛の身体の外側に延長されたもうひとつの身体であると同時に、網にかかった蠅にとっての環境でもある。身体とその環境を同時に揺らすことで、蜘蛛は、自分の外側にある世界へと直に届いていく。
実は人間もこうした知覚のシステムを持っています。元陸上選手で生態心理学者のマイケル・ターヴェイが研究したダイナミック・タッチがそうです。ターヴェイは次のような実験をしています。被験者の顔と右手の間に衝立てを設け、右手に棒を渡し、棒を見ないで棒の長さを当ててもらう[fig.7]。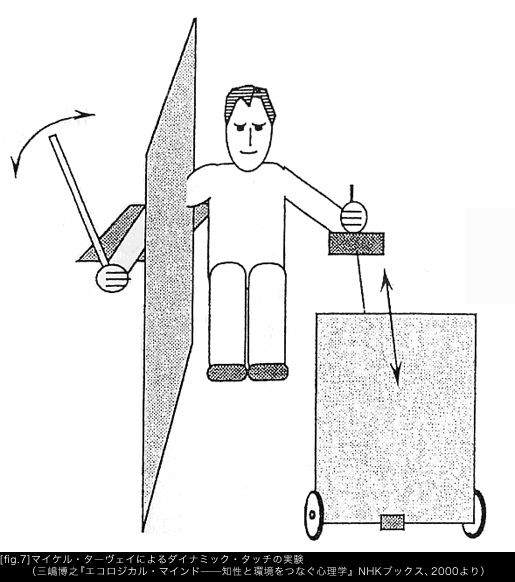
棒に触れる場所は一カ所、端だけしか持ってはいけない。端だけを持ってその棒の長さを当てるのです。すると、これが実によく当たる。ターヴェイが注目したのは、被験者が、棒の長さを当てようとするときに棒を振ることです。振ることによって棒の長さを当てている。ターヴェイは、棒の慣性モーメントが直接的に棒の長さとして知覚されていることを明らかにしました。
この研究を生態心理学者の三嶋博之さんが、紐の長さを知覚する実験へと展開しています[fig.8]。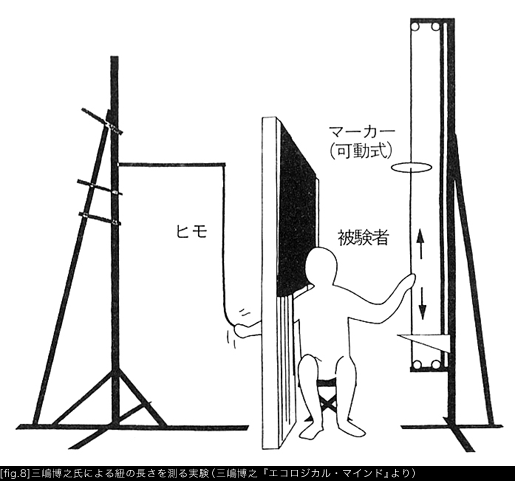
この実験では、紐を持った被験者がいろいろな手の動かし方をする。整理するとその動きは、下に引っ張る、横に引く、振り子状に動かす、回転させる、波立たせる、持ち上げる、の6種類になる[fig.9]。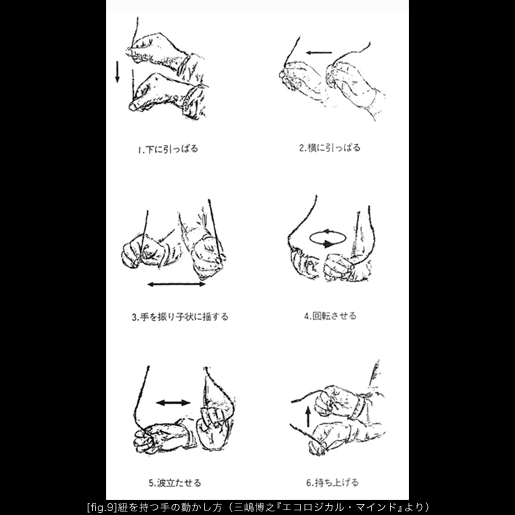
ここで三嶋さんが注目したのは、紐の動かし方が6種類に収束するという事実です。つまり、紐の長さを動きによって知るための行為は、紐がもつ不変な質との関わりのなかでおのずと決まってくる。その不変な質との関わりのなかで、紐の長さが、視覚を借りずに知覚される。ここで行なわれていることは、蜘蛛が網を揺らす行動と極めて近いものです。私たちは、映画館に座っている人間のように、ただ閉じ込められ動けない場所で世界を認識しているのはない。私たちは動かすことができる身体を持っていて、身体を動かすと同時に世界それ自体を揺らすことができる。そのようにして、自らの認識論的閉鎖性の外に向かって開かれていくことができる。

こうして、私は蜘蛛の知覚─行為システムを通して、映像という問題をプロジェクションの問題として考えることをやめることができるのではないかと考えています。映像という問題はすなわち、私たちが私たち自身の認識論的閉鎖性の内に閉じ込められているということにほかなりません。しかし私たちは閉じられているにもかかわらず外とコミュニケーションをとることができる。私たちは私たちの感覚する映像の内に閉じられてあるけれども、その映像は世界と身体の振動を通して外部へと開かれている。この閉鎖と開かれを考える実践のことを、映像の哲学という言葉で考えることができるのではないか。そんなふうに考えています。
柳澤
映像をプロジェクションではなく、ジャーキングとして捉えてみようという、とてもクリアな、非常に面白い提案をしてくださいました。
つづいて大橋さん、よろしくお願いします。