柳澤田実 プレゼンテーション〈人間の意識の呪縛〉、〈他者への生成変化〉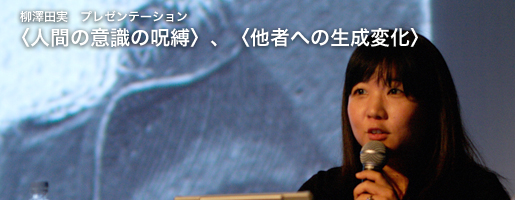
■〈人間の意識の呪縛〉、〈他者への生成変化〉
柳澤
先ほど倫理の可能性を知覚のほうから、つまり理念として上位に置くのではなく、ボトムアップに考えていこうというお話をしました。知覚というヒトがヒト以外の生物と共有している能力に依拠して、どう生きるべきかを示唆するような、ethicalな創作ができるのではないか。いわば生態学的観点からポジティヴな議論を立てようとしてきたわけです。生き物としてのヒトに希望を見出すこうした議論は、ここにいる私たちだけではなく、昨今さまざまな場所で始められていると思います。最近の出版の状況を見てみても動物が作る建築物に関する翻訳書などをはじめ、生態学的な関心が強く広まっていることを感じます。とはいえ、同時に私たちが人間である以上、知覚のうえに成り立つ「意識」という経験から逃げられないということは無視できない問題であるだろうと私は思います。今日は、知覚で捉えられているレベルと意識で捉えられているレベルによって構成される、人間の認識論(エピステモロジー)の入れ子構造について、またその構造を自覚的に問題にしている映像作品を引いてお話したいと思います。
意識以前に実現していることに何らかの可能性を見出すといっても、意識において捉えられていることと意識以前のもののギャップは、現実にはなかなか埋めがたいものとしてあります。意識において捉えられている一人称的な理解というものがいかに誤りやすいとしても、一方で知覚も完全に無垢なものではありませんので、概念的な思考によって世界の知覚経験の内容が変わっていってしまうことがある。ですから、両方のレベルをいかに架橋していくかということが非常に重要で、哲学はもちろん、そもそも知覚と思考を架橋することによって生み出される芸術作品の多くがこの問題に触れていると思います。
今日ご紹介したいのは、チャーリー・カウフマンという映画脚本家です。彼は、《マルコヴィッチの穴》(1999)という映画で一躍有名になった人物で、最新作《脳内ニューヨーク》(2008)では監督もしましたが、それまでの5作品はすべて脚本のみを担当しています。私は、この人の脚本が一貫して2つの問題を追いかけていると考えています。それが、〈人間の意識の呪縛〉と〈他者への生成変化〉です。「意識は呪いである」という非常に印象的な言葉から始まる《マルコヴィッチの穴》は、他者の脳のなかに入るという荒唐無稽な設定で、最終的には主人公の意識が赤ん坊の脳のなかに閉じ込められてしまうという悪夢のような終わり方をする作品です。
今日ご紹介したいと思ったのは、3作目の《アダプテーション》(2002)です[fig.2]。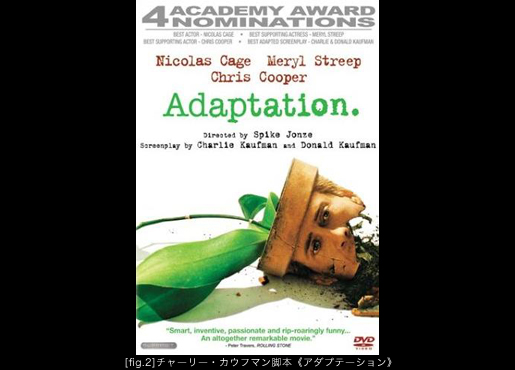 この作品は、私たちが世界をとらえる際の認識論の入れ子(ネスティング)構造をイメージ化することに成功しており、まさに映像であるからこそできることを自覚的に実現していると思います。この作品には、ヒトの経験世界を構成するたくさんの入れ子構造、メタ構造が登場するのですが、アダプテーションというタイトルにも、身体・自然のレベルと意識のレベルの二重化が示されています。つまりダーウィンが進化論で提出した、生物の環境への適応・共進化を表わすアダプテーションと、カウフマン自身がこの映画作品のなかに出演し、物語を脚色するという意味でのアダプテーションがかけられていて、いわば生きることと物語をつくることがオーヴァーラップし、入れ子構造化しているこの作品の内容を示しているのです。
この作品は、私たちが世界をとらえる際の認識論の入れ子(ネスティング)構造をイメージ化することに成功しており、まさに映像であるからこそできることを自覚的に実現していると思います。この作品には、ヒトの経験世界を構成するたくさんの入れ子構造、メタ構造が登場するのですが、アダプテーションというタイトルにも、身体・自然のレベルと意識のレベルの二重化が示されています。つまりダーウィンが進化論で提出した、生物の環境への適応・共進化を表わすアダプテーションと、カウフマン自身がこの映画作品のなかに出演し、物語を脚色するという意味でのアダプテーションがかけられていて、いわば生きることと物語をつくることがオーヴァーラップし、入れ子構造化しているこの作品の内容を示しているのです。
さて、物語は、ノンフィクション作家スーザン・オーリアンが著した実在の書『The Orchid Thief』(2000)という、チャールズ・ダーウィンのように蘭に魅せられた男の話の脚色を依頼され、脚本化カウフマンが七転八倒するという内容です。作品内部のドラマでは、ダーウィンが書き記した、ある独特な形をした蘭とその蜜を吸うために共進化した蛾の舌に見出されるアダプテーションと、人間が他者と出会い変化していくというアダプテーションの2つが重ねられています。さらに興味深いのは、この作品が、人間の認識の枠組み(エピステモロジー)によって捉えられる世界というものが複数のユニットやレベルで成り立っているということ、それゆえに、世界をどのスケールで捉えるかによってユニットが変わるということを、映像で表現しているということです。つまりこの作品は、主人公チャーリーの意識の領域、チャーリーが読む本の語り手であるスーザンの意識の領域、彼らを包み込む環境世界、脚色に苦しむ自分自身をドラマにしている最後に立ち上がる主体=チャーリーの意識、という4つのレベルによって構成される入れ子構造をなしています。そして、映像を観る私たちは、複数の思考のレベルを行ったり来たりするチャーリーの逡巡に付き合うことになるのです。
──《アダプテーション》一部鑑賞──
世界を構成する進化論的なレイヤー・自然のレベルを見せていって、最終的には、さまざまなレベルに思考を巡らすチャーリーの意識が前面に出てくる入れ子構造。このように複数のレベルがレイヤー状に折り重なっていることを映像は表現することができるわけです。この人間の世界を構成する認識、エピステモロジーの問題については、『精神の生態学』(Steps to an Ecology of Mind, 1972)[fig.3]を書いたグレゴリー・ベイトソンが極めて興味深い議論を行なっています。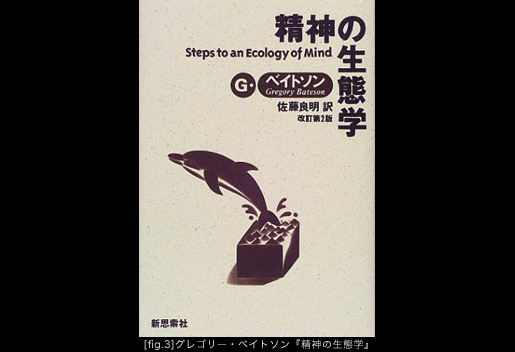
今日テーマとなっている生態学、エコロジーという立場を明確に立ち上げた人としても知られるベイトソンは、そもそも精神と自然を分けることは間違っていると考えていました。彼は、自然科学が私たちの抱く幻想や妄想を主観的だと切り捨て、現実のリアリティを純粋な実体、客体のみに還元していくことを批判し、主観的で付帯的な現象をポジティヴに位置づける可能性を探求した人でした。ベイトソンには主に2つの提案がありました。ひとつは有機体と環境のシステム全体を精神として捉えていこうということです。今日隆盛を極めている脳科学とベイトソンの議論とをどのように架橋するかということは難しい問題ではありますが、少なくとも私たちの精神とは、単に脳内に限定された働きとして独立して取り上げられるべきものではなく、有機体と環境によるシステム全体だと主張したわけです。そして2つめの提案として、このシステムにはプレローマとクレアトゥーラという2面性があるとしました。プレローマは力や衝撃の因果関係によって説明できる物理的世界、クレアトゥーラは多様な差異の生成によって説明できる情報の世界です。ベイトソンは、クレアトゥーラに可能性を見出しており、すべての差異を生み出していく精神の働きはクレアトゥーラとして連続しており、これが生物の大きな生態システムをなしているのだと述べています。先にも述べたように、ベイトソンにとっての精神とは、「考える」という働きを担うものとして限定されるべきではなく、行為者が環境から意味を見出すというギブソンが「知覚」という概念で語った対象と限りなく近いものです。
私たちの身体も皮膚によって限定されるものではなく、身体とその周りにある環境までもが地続き・情報のサーキットになっているという前提で、そのすべてを「精神」と呼んでしまおうというのがベイトソンの立場なのですが、問題は、こういう開放システムの作動を私たちはいかにして経験できるのか、ということだと思います。つまり意識の閉塞に苦しむ人に、「それは誤謬なんだよ、すべては情報のサーキットとして連続しているんだよ」と言ったところでどうしようもない。実際にその開放システムを生きているということを経験できるようにならなければならないわけです。このような経験を与えるような、いわば意識の閉塞から抜け出すための処方箋づくりはどのような作品や装置によって可能なのでしょうか。先ほどのカウフマンの作品は、私たちが抱える閉塞的な部分と、すべてがサーキットとして連続している部分、あくまでもその両方のレイヤーを見せるという意味では成功していると思いますが、より端的にベイトソン的な精神の開放システムを経験させることは、作品としてどういうかたちで可能なのでしょうか。この問題をぜひ今日の討議のひとつの主題として提示したいと思います。特にこのベイトソン的な作品の可能性については、ドミニク・チェンさんがソフトウェア開発を通じて試みていることだと推測しています。
それでは次に平倉さん、よろしくお願いします。