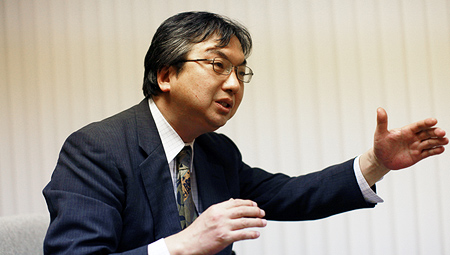異なる身体、異なるシステム
河本
こんにちは。私は以前からとてもラグビーが好きで、冬の秩父宮競技場にも見に行っています。
平尾
よろしくお願いします。そうですか、きっかけは何ですか?
河本
いやいや、平尾さんですよ。新日鉄釜石が連覇を続けていた頃からラグビーは見ていましたが、年中行事のように見るようになったのは平尾さんがスーパースターになっていく時期です。もちろん1985年の同志社大学と釜石の日本選手権も見ているのです。当時は1月15日の日本選手権が終わらないと僕の正月は終わらない。仕事始めはその後だと勝手に決めて、毎年ずっと観戦していたのです。厳密に言えば、京都市立伏見工業高校時代の試合はよく知らないのですが、その後の同志社大学時代の平尾さんはずっと観ていました。あの頃の同志社には学生ですでにナショナルチームに入っていた選手が3名もいて、えらく強いなと、だれもが思っていました。当時はまだ僕にとっては大八木淳史さんがスーパースターで、フォワードで相手選手を2、3名引きずって突破し、ラックを作る。そこに人数的に余力のできたバックスがボールを支配してつないでいくというような見方しかできていないのです。要するにもっとも派手なところしか見えていなのです。ところが試合後のインタヴューで大八木さんが「平尾がこうやれって言うからこうやっとるんだ」という話し方をする。そのため平尾さんが全部組み立てているんだなと思っていました。テレビだとそのあたりが見えにくいのです。テレビの場合、派手な突破や派手な当たりしかしか撮らないので、司令塔のゲーム作りがうまく見えなかったのです。その後の神戸製鋼時代もずっと観ていましたが、いつ頃だったかあまりラグビーを観なくなった時期があります。ここ10年くらいはサッカーのほうが面白くてね。
今週の日曜日(2008年12月7日)の明治大学と早稲田大学の試合で、久しぶりに、精確には8年ぶりか9年ぶりに明治が早稲田に勝ちました。あの時にわかったのですが、モールの引き倒しができるようになったので、明治は本来困るはずですよね。モールの場合、集団でボールを抱え込むようにして立ったまま前進していきます。あれを止めるのはどのチームにとっても大変です。ラグビーの場合、ボールに対して後ろから働きかけなければならないので、少しでも横から攻めた形になると、ただちに反則になります。このモールを得意としていたのが明治です。ところがモールを手前に引き倒して崩してもよいというルール改訂が行なわれて、明治は得意技のモールが使えなくなりました。その結果シーズン全体の明治の成績は芳しいものではなかったようです。
あの規則ができたために、8人で組むような大型のモールはやっていませんでした。ところがそれを3、4人の小さなモールでやっている。2つの小さな集団を作り、ひとつの小さな集団が引き倒されると、次の集団がボールを拾い上げて新規のモール状態を作っていく。モールを小粒のパーツにして、引き倒されても継続できるようなモールの形が少しできていた印象でした。長い距離を大型のモールで進むのはもう無理であっても、ちょっと違う形ならば、継続できるのかなという感じを受けました。結局明治は運もあって24対22で早稲田に勝ったのですが、要するに僕の楽しみはそういったことを観ることなんです。
平尾
なるほど。よく観ていらっしゃいますね。
河本
僕はシステム論を専門にしていまして、これまでいろいろな開発をしてきました。なかなか難しい理論でお話すると非常に長くなるのですが、それを考えていた時の最も典型的なイメージが、平尾さんのラグビーと中原誠十六世名人の将棋でした。ところが将棋の世界ではその後羽生善治が登場し、将棋のシステム自体が完全にヴァージョン・アップしたのです。ああ、こういうことかという印象を受け、それで対談集『システムの思想──オートポイエーシス・プラス』(東京書籍、2002)を作りました。あの本にも企画段階では、平尾さんとの対談が予定されていたのです。
例えば南米のサッカー、とりわけブラジルのロナウジーニョのボール処理の仕方を見ていると、ある程度体の重心を下げて、股関節の柔らかさを使っていることがわかります。股関節が柔らかいから重心を下げても足元で処理ができる。ところがドイツのサッカーはまったく違います。彼らはものすごく身長が高くて図体がでかいのだけれども、足元が上手い。体を上げた状態で足に自由度を持たせるためには、上でバランスを取らないといけないですね。するとどうも、ドイツ・サッカーの基本は肩幅にあるらしい。肩幅の回転やバランス制御を使って、足下を上手くコントロールしている。ドイツ・サッカーの体の活かし方と、南米サッカーの体の活かし方には相当大きな差がある。それぞれに応じたシステムの作り方をしているのだと思うのです。ゲームですから、最後はどちらがたくさん点を採るかで勝ち負けは決まるわけですが、それぞれに異なる身体の機能を使ってシステムを成立させている。それに比べると、ラグビーはやはりまだ足が速いとか、遠くまでボールを蹴ることができるといった、量的な技能によって成立している部分が大きいと思うのですが、それよりももう一段階細かい身体特性を活かせるような領域が、もうそろそろ出てくるんじゃないかという感じがしているのです。
身体的優位性と技術の世界
平尾
そうですね。どちらかというとサッカーのほうが器用さが必要です。かといって、ラグビーがそちらに近づいていくのかというと、それはちょっとわからない。これと関係してくるのがルール性の問題だと思うんです。ルール性からいうと、ラグビーはボールを持って走ってよいけれども、サッカーではそれができないわけで、ボールに触れるその一瞬の感触、扱い方においては、力というよりもまず技術が優先されますね。ましてラグビーでは身体が当たってもよいわけですから、ゲームのなかで身体的優位性がものすごく大きな部分を占めてくるとは思います。ただそれを克服していくためには、今度は器用さとか技術、巧みの世界みたいなものが必要になってきます。ボールを持って何歩走ってもよいというルール性、そしてコンタクト・プレーの要因性から見れば、日本のように他国と比べて体も大きくないし、スピードもあまりないチームでは、身体的優位性以外の部分を含んだ戦略が際立ってこないと、なかなか勝てないと思います。
河本
プレーヤーをはじめ現場の方々ははるかに悔しい思いをされていると思いますが、ラグビーの国際試合は観ていて本当に悔しい思いをします。試合をかたちづくる要素には、個々の選手の体力、走力、脚力、体重はもちろん、蹴った球の距離、正確さ等々、実にいろいろなことがあると思うのですが、こと国際試合では、大きな体力差そのものを見ている者も思い知らされるわけです。結局のところ体力差が絶対的にあって、それを埋めるには基礎的な能力がある人をかき集めてこなければならないと落ち着いてしまうところがある。でも待てよ、そう落ち着いてしまう前に、もっとたくさんの選択肢が出てこないのかな、という感じがいつもするんですね。
平尾
先生のおっしゃるようになったほうが、ゲーム性の面白さが発揮できるとは思います。ただ、今どこが強いチームかと問われると、基本的にはやはり身体的優位性が強いチームです。そのバランスを補うための戦略性、戦術性がゲームにおいてどれだけのウェイトを占めているかというと、どうなんでしょう。例えばこの間(12月6日)、関東大学対抗戦で帝京大学が優勝しましたけれど、やはり身体的優位性が高いですよね。それがラグビーのなかなか難しいところです。昔と比べて体もだいぶ大きくなってきたということもありますし、まして今や外国人選手をたくさん使いますよね。それが海外チームとの溝を埋めているところがある。ただ日本代表チームの話になった時に、どこまで外国人枠の使用が社会的に容認されるのかということも含めて、溝をどう埋めていくのかをめぐっては、われわれ自身の視点を持っていかなければならないと思います。ただ、繰り返しになりますが、身体的優位性、つまり体の大きさ、持久力というよりもスピードと筋力と体力、これがあるとだいぶ違います。
TrackBack URI : https://www.yebizo.com/jp/archive/forum/specialdialogue/wp-trackback.php?p=67
Comments (0)