榑沼範久プレゼンテーション 感覚の座、ユニットのジャストなチューニング
■感覚の座、ユニットのジャストなチューニング
榑沼
今日は過去2回のラウンドテーブルと違い、登壇者5人と「視聴者」の皆さんが対面する配置になっています。それに、基本的に5人で話をしてきたこれまでの回とは違うので、今日は会場の多くの皆さんにも向けて話をしなければと思っています。ところで、これまでは明るい部屋で話し合ってきたのに、今日は暗い部屋にスポットライトですね……。私はラウンドテーブルが始まると手元の紙にいろいろ言葉を書いていき、それを話に織りこんでいくのですが、今日は老眼も手伝ってか、白紙に書いた文字がよく見えません。ラウンドテーブルの面白さは私にとって、自分が事前に考えていなかったことが、この場から与えられるからでした。複数の個体が組み合わさることによって、個体と異なるユニットが立ち上がる。おそらく私の身体は、このユニットによって生じる「ジャストなチューニング」を探し求めているはずです。そして、この「ジャスト」を求めるのが、私の身体それ自体の「倫理」でもあると考えています。それが今、なかなか「ジャストなチューニング」が見つからない……。「歌」を探し損ねています。洞窟のなかで紙に書いた言葉がよく見えない、そんな状態で杖をつき、何とかシステムを組み直そうとしているところです。
さて今日は皆さんに、トランプの写真を見ていただこうと思います[fig.12]。
クローバーの4です。特別な仕掛けをしているわけではありません。手品をするわけではありませんからね。表面が泥で少し汚れていますが、普通のトランプです。
私は20代の後半、イギリスのカンタベリーにあるケント大学大学院映像研究科に留学していました。とはいえ、絵画にも映画にも写真にも、ほとんど関心を失いかけているなかでの渡英でした。自分自身も含め、腹の底から言葉や感情を発しない空気の日本の大学院に、かなり嫌気がさしていたということもあります。本当のところは、自分の不能にぶつかっただけです。おそらく意識の呪い、自分の意識の閉鎖性から出ることだけを求めて、20歳の頃から哲学や映像や音を求めてきたのに、その可能性が自分のなかで信じられなくなったのでしょう。自分のしていることが、生きている身体、そして生きていることと、どのように関係しているのか。つながらなくなってしまったのです。
当時、かろうじて興味を抱いていたのは、思い起こせばMRI(核磁気共鳴映像法)でした。平倉さんから蜘蛛のジャーキングの話が出ましたが、私はそれを見てMRIを連想しました。核磁気共鳴映像は装置によって作り出された磁場に人体を入れ、送信された波動が人体内の水素原子から戻ってくる速度のズレを数値化して、映像化するものでしたよね。こちらから働きかけると、それが引き起こすズレがデータとして抽出可能になる。MRIの静止画は平面ですし、そこに時間は欠けているように見えますが、その静止画のなかに実はいくつものタイムラグが埋めこまれています。私はMRIも含めた「医療映像史」を書こうとしました。しかし、自分のしていることの意味が崩れていく感覚は、主題や素材を変えても変わりませんでした。
ケント大学での指導教員は、音楽理論・批判哲学にも詳しいDavid Reason先生でした。先生は幼い頃に罹ったポリオのため、足をうまく動かすことができず、電動車椅子に乗って生活をしていました。「私は後天的なオプティミストだが、先天的なペシミストだ」と語っていたこともありました。「私は一生、ヒッチコックの《裏窓》の主人公だ」と言って、豪快に笑うこともありました。私はあるとき、先生に告白したのです。「自分の書くものが、すべて屑に思えます」と。すると先生は笑って、「君は自分の書くものが屑と言うけれども、私の研究室の部屋のなかで屑ではないもの、それを指してくれ」と言ったのです。名著と言われるものもたくさんあるわけですが、そのときの自分には、すべて屑に思えました。そして、「すべて屑です」と答えたら、先生は微笑みながら、「そうだろう。私も同感だ。だから来週、屑をもうひとつ持ってきなさい」と(笑)。
泥で少し汚れたトランプは、このDavid Reason先生からの贈り物なのです。これも「屑」という意味ではありませんよ。帰国するとき、先生の研究室に挨拶に行くと、部屋の壁を指さして、「あそこに貼ってあるトランプを君にあげよう」と言うのです。電動車椅子に乗っている先生は、狭い室内ではそう機敏に動けませんから、私が壁に近づきます。泥で少し汚れた、普通のトランプです。意表をつかれ、困惑の表情を私は浮かべたのかもしれません。先生は続けます。「そのトランプは15年前に、このダーウィン・カレッジの建物の前で、雨の日に拾い上げたものだ」と。車椅子で移動する彼の視点の位置だからこそ、雨道に落ちているトランプに注意を向けることができたのかもしれません。マルセル・デュシャンやジョン・ケージを好む先生らしい行為とも思いました。

しかしそれにしても、15年間も壁に貼ってあったと聴くと、あまりに貴重に思え、簡単に頂くわけにもいきません。しばらく躊躇していたのですが、先生に促されるままに、思い切ってトランプを壁から剥がしたのですね。すると、トランプが貼ってあった部分だけ、壁が日焼けしていなかったのです。疑っていたわけではないのですが、トランプの跡の四角形とその周囲とのコントラストを目の当たりにすると、壁が急に時間の厚みを帯びてきたわけです。そして部屋がひとつの均質空間ではなく、さまざまな時間のズレが織りこまれた混成空間として現われてきたのです。
思わず、「やはりこれを頂くわけにはいきません」と私は口にしました。するとReason先生はこう言ったのです。「君がこのトランプを剥がしたことによって、私は一枚の写真を手にすることができた。君はトランプを手にして、私は写真を手にしたのだから良いではないか」と。すぐに反応できなかった私に、先生は鋭く切りこんできたと記憶しています。「もしかすると、君はカメラがないと写真は撮れないと思っているのではないか?」。
砲台から撃たれたわけではありませんが、ベイトソン風に言えば、何か「引き金を引かれる」出来事だったと思います。カメラを使ってはいなかったけれども、私はトランプを剥がしたときに、いわば開いていたシャッターをそれと意識せずに閉じたのです。歴史上初めて写真を撮ったといわれるニセフォール・ニエプスが撮影したのは、日照時間が長い季節のこと、露出時間は8時間とも20時間とも言われています。そのニエプスは写真術のことを、太陽を意味する言葉「ヘリオ」を合わせて、「ヘリオグラフィ」と呼んでいました。Reason先生が「手にした」のは、まさに「ヘリオグラフ」です。先生の部屋の窓やブラインド、そこから射しこむ太陽の光。それが少し「暗い部屋」の壁に、15年間、太陽の光を描きつけていたのです。
われわれはカメラのような眼で撮影した映像を脳に送りこみ、脳内で何かしら現像処理を行ない、その「写真」を世界として認識していると思っているかもしれません。しかし、『物質と記憶』(Matière et mémoire: Essai sur la relation du corps à l'esprit, 1896)[fig.13]を書いた哲学者アンリ・ベルクソンに言わせれば、その考えは間違っています。もし「写真」があるとすれば、それはわれわれの感覚器官や脳のなかにではなく、われわれの周囲で光がさまざまに織りなされている場所、そうした相互作用が起きている場所に、すでにある。そうベルクソンは論じます。脳や眼の基本的な役割は、人間とは無関係にすでに存在する無数の「写真」のなかから、行動や記憶のために「写真」を選び出すことです。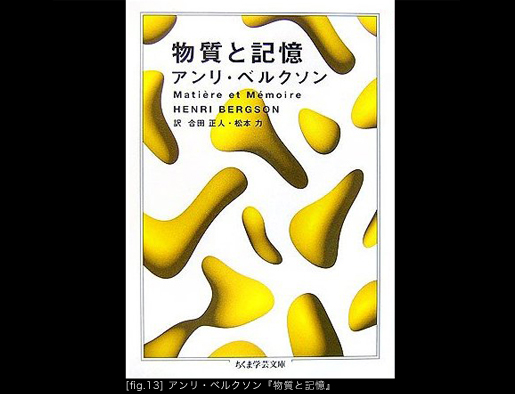
そうだとすれば、選び出された「写真」と、われわれと無関係に生じている無数の「写真」とのあいだに、本性の違いはありません。記憶や脳内作用に厚塗りされた「写真」もあるにせよ、「写真」はその先端において意識の外に触れている。Reason先生からの贈り物に「引き金を引かれる」出来事が生じてから、ベルクソンの『物質と記憶』はこのトランプと共鳴してやみません。人間的な、あまりに人間的な作品や意識から、私は映像を引き離してみたいのです。
最後にもうひとつ別の話を。今、冬季オリンピックが行なわれていますが、長野オリンピックでスピードスケートの清水宏保選手が金メダルを取ったとき、その滑りをテレビで観て、私は涙を流してしまったことがあります。あまりに人間的な話ですみません(笑)。涙に嘘はあるのか真実はあるのか難しい問題ですが、いづれにしても自分の意識にとって不透明な涙はあるでしょう。涙は「混合物」で、なぜ自分が涙を流しているのかわかりにくい。しかし、日本人選手が努力のすえに金メダルを獲得したから涙が流れた、というわけではないのです。それに私はスケートのファンでも、清水選手のファンでもありません。清水選手が爆発的なスタートを切り、最初のコーナを疾走している映像を観て、私は涙を流してしまいました。
スケートという競技は、考えてみれば非常に不自然な営みです。とくにトップレベルでは、スケートのエッジは磨きに磨きぬかれ、氷はこれ以上なく均質な表面と化している。なぜ、そのような不自然なことをするのか。自然の有機的な組み合わせを切断し、不自然なものと不自然なもの、不自然な肉体と不自然な表面を組み合わせて、ひとつの「ジャスト」なユニットを生成することは可能なのか。異質で不自然なものどうしをどのようにモンタージュして、違う「ジャスト」なシステムを作り上げることができるのか、という実験をしているのだと思います。他の競技にも、それぞれの実験があるでしょう。そうした実験に挑戦する選手たちの動きのなかで、私は清水選手のコーナリングに、何か凄いデッサンのような「筋」「蛇行線」を見たように感じたのですね。
私が競技場でこの滑走を生で見ていたならば、リンクまで距離を置いた観客の視線で終わってしまったかもしれません。清水選手がスーッと目の前を通り過ぎ、頭ごと向きを変えて視線で追いかけるのが精いっぱいだと思うのです。しかし、あのときは清水選手の運動をカメラの運動が迎い入れ、スケーターの運動とカメラの運動が形成するひとつの映像ユニットを、私自身が迎え入れる、そうした「入れ子」構造が作られたように感じます。2回目のラウンドテーブルでは、ベルクソンの『持続と同時性』(Durée et simultanéité, 1922)を参照しながら語った事態です。複数の動きが組み合わさることによって生じるユニットが、「ジャストなチューニング」を立ち上げたのかもしれません。「感動」をこうした場であからさまに語る人は少ないのでしょうが(笑)、考えてみれば、「感動」とは「感」が「動」くと書くわけですから、文字通り感覚や感情の座が新しいユニットの形成とともに動く、そういうことではないでしょうか。われわれの身体との関係で映像の機能を考えるには、案外こうした場面が適しているように思います。
柳澤
ありがとうございました。最後ドミニク・チェンさんに引き続きお願いいたします。当初10分と言われていていましたが、緊張も重なって少しずつ押しています。ドミニクさんにお話していただいてから、議論というかたちでまとめたいと思います。