映像の遠近、映像のオルタナティヴ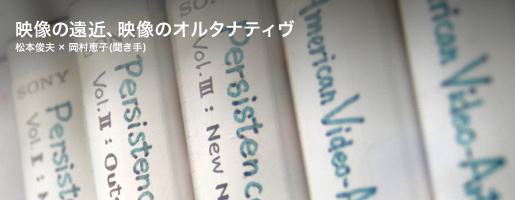
映像でしかできないこと、とは
「オルタナティヴ・ヴィジョンズ」というテーマから導かれる「映像でしかできないこと」について考えると、歴史的に「映像の固有性」が強調される背景には、映像が言葉のイラストレーションとして扱われ、映像本来の力が解放されていない環境へのいらだちがありました。映像の自律性を明確にしないと、映像はいつまでも文学や演劇その他の従属物でしかないという、近代芸術の原理に則った考えです。しかし、映像は多元的な要素の全体として独自な力を発揮していくものであって、その多元性を表現へと統合する方法のなかに映像固有のものがあると理解したほうがよいと僕は考えています。
実験映画の手法はその独創原理を排他的に主張するかぎり、モダニズム、あるいは純粋主義と同じ基盤にいると言えるでしょう。実験映画には、コンセプトを重視するものもあれば、視覚的なイメージを重視するものもあります。しかし、非本質的なものの排除を極端に突き詰めると、生きた表現の大事なものがぬけてしまう。僕は映像の本質はむしろハイブリッドな性格と構造にあると思う。そこにほかの芸術分野にない映像の固有性があり、オルタナティヴもそこから生成するのです。
またこうも言えるでしょう。映像は言語に還元できない、ある種の虚構です。それがあたかも現実であるかのごとく、リアルな実感をともなって見る人の間に固有な意識状態を創り出す。そこでは言葉や音、運動、色、形などのさまざまな要素が複雑に絡み合い、映像表現の魅力が生まれているのです。ですから、映像は純粋主義や還元主義とは相性が悪いのです。
実験映画は、ある意味では純粋主義の道を走りました。アメリカのジョナス・メカス(Jonas Mekas、1922─)等が1970年にマンハッタンのパブリック・シアターに創設したアンソロジー・フィルム・アーカイヴスという実験映画の拠点に以前行ったときのことですが、上映空間を真っ黒に塗り、スクリーンを吊って、席をパネルのボックスで覆って、隣の人も前の人も見えない環境にして自分だけになるのです。そうすると、暗闇のなかにスクリーンが浮き、鑑賞者が映像だけと向かい合う、完全な純粋空間ができる。一切のノイズを排除して、そこに人がいること自体が邪魔になるという、なんとも倒錯した状況になっているのです。実験映画のなかには面白い、豊かな作品も多くあるわけですが、感情を表わすことが一切禁止されているかのごとく静まりかえり、スクリーンと1対1の純粋な対話が強要されるこの環境、さらに実験映画を純粋主義的アートとして扱うこの方法は少しおかしいのではないかと僕は思いました。なにも祭壇に祀り上げて見るものではないだろうと。実験映画とはもっと荒々しいものだったし、ノイズそのものだった。ですから総じて、芸術であることを強調する必要のある場合と、あまり芸術と言わないほうがよい場合と両方あります。特に近代的な芸術観に限定して芸術という呼び名を使うことには少なからぬ問題があるのです。

認識装置としての映画・写真
フランスの映画史家レオン・ムシナック(Leon Moussinac、1890─1964)は、「映画は夢の工場である」と言いました。われわれも日常「まるで夢のよう、まるで映画みたい」という表現を使います。この擬似的体験の世界は映画の登場以前にはありませんでしたから、僕らの現実そのものを見る見方が変わったのです。ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin、1892─1940)は、写真が登場した際に「人間の知覚が変化した」と本質的な問題をついています。都市のさまざまな風景やファッション、人間の振る舞いなどに対して、映画・写真的な文化モデルが影響を与えたのです。映画は新しい時代の感性、欲望を先取りして、なんらかの形にしていく。特に映画が生まれた時代が機械の時代であったことを考えると、映画は都市に生まれるスピードや、新しい建築の物質感などが放出する感覚などと共振し、それらが総合的に時代全体の空気を作っていったのです。また、映画は目で見る以上に全身体的に見るという経験をともない、それゆえに観客は映画館という空間で身体的な反応を共有するわけです。ある種の共同体としての観賞の集団形式である「間身体性」あるいは「間主観性」が成立したのも映画というメディアがもたらした感性だろうと思います。
現在は、技術の刷新にともなって映像の形態が多様化しています。古典的な映画の時代には、複製技術による「唯一性、アウラの消滅」が重要なモメントとして文化の特性を生みました。『複製技術時代の芸術』(1936)(Das Kunstwerk im Zeitalter Seiner Technischen Reproduzierbarkeit, 1936)におけるベンヤミンのこの指摘が西洋のオリジナル優位主義を逆転させたのです。ところが、映像の時代が展開すると、古典的な映画館だけではなく、街や家庭、どこにいっても映像だらけ。ブラウン管にとどまらず、実に多様なメディアに映像が散在していったわけです。そうすると、単にオリジナルと複製という図式では捉えきれない。累乗化するコピーのコピーは、オリジナルとコピーという主従関係を攪乱します。デジタル・コピーはオリジナルより品質劣化しているとも一概には言えません。さらに、現在のデジタル技術が像そのものを変形、加工し、オリジナルなきコピーである「シミュラークル」に満ちた文化特性を生んでいく。このような時代の映像は古典的映画時代の映像と明らかに異なり、前にはなかった高度のシステム・レヴェルの何かが時代を引っぱる支配的な原理になる。文化の問題としては、そこをつかまえないと、変化の問題点が見えないのではないかと思います。